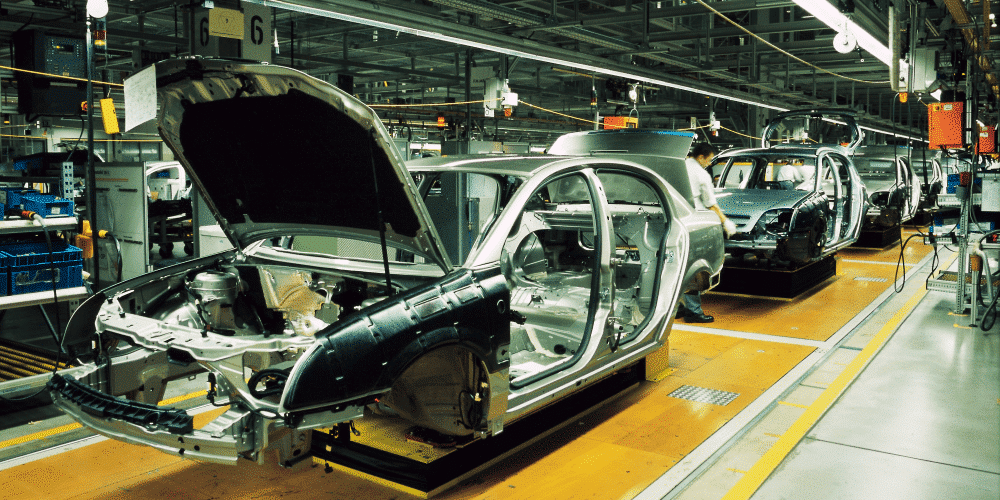インドネシアの二輪四輪産業に多い組立系のマスプロダクション工場における生産管理業務の中では、生産計画と負荷計画は表裏一体の関係にあり、生産計画が数量ベースで立案される以上、負荷計画も機械あたりの数量ベースで見たいという要求が強く、一般的には日単位またはシフト単位での生産計画と負荷計画が求められます。
インドネシア人の計画作成担当者の頭の中では「今日(またはシフト)この機械で何個生産するか、何個分キャパオーバーするからその分を何日に生産するか、キャパが足りなければ何時間残業が必要か」という思考が働いており、システム上で生産数量(Production)、消費数量(SalesまたはDemand)、在庫数量(Inventory)を対比して見るためのPSI表が求められます。
計画は実績と対比して進捗を確認することに意味がありますので、例えば1週間分の計画を作成する場合、計画作成時に表示される数量はすべて現在庫数量に基づく予測ベースの数量であり、生産実績が入力されるたびに在庫数量の推移が変化し、次の1週間分の計画作成時にその時の現在庫数量に基づく予測ベースの数量にリセットされます。
インドネシアの計画系業務をシステム化する際には、分刻みの細かいスケジュール管理を目的とするよりも、日(またはシフト)単位で入力される生産実績に対応させて同じ単位で参照できるほうがシンプルで、現場の計画作成担当者に受け入れられやすいと考えます。
当ブログではインドネシアの製造業者様で生産計画(スケジューリング)業務のシステム化の必要性を感じているものの、具体的に何から手を付けたらいいのか分からないという方にとって、インドネシアに合った製造業システムとは何かをイメージするための一助となるような生産スケジューラについての記事を書いています。
MRP(資源所要量計画/製造資源計画)からAPS(先進的計画&スケジューリング)への発展
受注オーダや内示から製品在庫を差し引き最低在庫を考慮した上でMPSを作成しますが、本来MPSは、顧客サービスの観点から出荷スケジュールや内示(Forecast)を重視する営業部門と、現場の事情を考慮したい生産管理部門(Production Planning and Inventory Control=PPIC)の双方の合意をもって作成される最終製品の生産計画です。
インドネシアの場合、MPSは生産管理部門が営業部門から受け取った内示と出荷スケジュールから機械的に作成し、営業部門もMPS作成段階で特に介入することは少なく、出荷時に納期遅れが発生しそうになるとあわてて現場におりてフォローする、という光景が日常であるように感じます。
MPSをもとにMRPの目的は通常生産時に正味所要量を製造するためのグロスの生産計画を作成することであり、MRPリードタイムずらしにより作成した生産計画は、現場の調整能力や生産準備(能力計画・販売計画)など人間の努力があってはじめて成立します。
これが限界に達したときに生産計画と能力計画がアンバランスになり、MRPから効率の悪い製造指図が発行されるようになった結果、生産能力が十分あるにもかかわらず不必要な残業や休日出勤が発生したり中間在庫が滞留したりします。
この問題を解消するためにタイムバケットを設定しない有限能力能力計画を考慮した先進的計画&スケジューリング(Advanced Planning and Scheduling=APS)の導入が検討されます。 MRP(資源所要量計画/製造資源計画)からAPS(先進的計画&スケジューリング)への発展 生産管理システムのコアはMRP II(製造資源計画)であり、MRP IIのコアがMRP I(資材所要量計画)で、正確なMPS(基準生産計画)を準備することが重要です。受注からMPSを生成しMRPで製造オーダを生成し負荷平準化後に購買オーダを生成するプロセスを一気通貫で行うのがAPSです。 続きを見る

生産スケジューラAsprovaのスケジューリングロジック
生産スケジューラAsprovaのリスケジュールのロジックの中で、リスト生成フェーズにてオーダテーブルからオーダリストを生成するのがオーダ収集コマンドであり、作業テーブルから作業リストを生成するのが作業収集コマンドです。
コマンド実行フェーズのオーダ展開(Explode orders)では、自動補充機能によってオーダリストを満たすように製造BOMを参照しながら、オーダの作業入力指図の不足分を補充オーダとして生成し、オーダリストに格納されている登録オーダと補充オーダに対して作業入力指図と作業出力指図を生成します。
オーダ割付/紐付け(Assign/peg orders)にて、ディスパッチングルールと資源評価のプロパティを見ながら作業使用指図を生成し、作業リストから作業割付けしますが、仮割付で一旦すべての候補資源に割り付けた後、実割付で資源評価から最も評価の高い資源に割付け直します。
オーダ間の紐付がオーダ展開時とオーダ割付/紐付け時の2回行うのは、在庫MINなど割付結果を元に再度FIFOで紐付け直す必要が出るケースがあるからです。 生産スケジューラAsprovaのスケジューリングロジック 生産スケジューラAsprovaは、オーダーリストまたは作業リスト生成フェーズの後に、コマンド実行フェーズでオーダ展開コマンドがBOMを参照しながら作業入力指図と作業出力指図を生成し、オーダ割付/紐付けコマンドが作業使用指図を生成することで資源に対する割付を行います。 続きを見る

生産スケジューラによる無限能力山積みと有限能力山崩しの違い
インドネシアの製造現場では、機械やラインのシフト単位、日単位のキャパに対して何個出来高を積み上げられるかという数量ベースの発想で生産計画が作成されていますが、長年Excelのセルを1シフトまたは1日と考えて生産計画を作成していれば、この発想になるのが普通です。
一方で生産スケジューラは、8:00~17:00のような稼働時間の空いている時間帯に作業を割り付けていくという時間ベースの発想で、両者の違いはシフト別日別にオブジェクトを生成するか、製造指図単位にオブジェクトを生成するかの違いと言えます。
生産管理システムのMRPはBOMを参照し所要量計算し数量ベースで日別にオブジェクトを生成しますが、設備の負荷はラインマスタ(設備能力)と品目ラインマスタ(標準負荷)という独立した別のマスタから無限山積みで計算され、マニュアルで負荷平準化を行う前提で設計されています。
ライン別に品目別の標準負荷(サイクルタイム)を設定し、オーダ数量に応じてラインに何分負荷をかけるかを計算し、リードタイム(日)ずらしした日に山積みして1日あたりのライン能力とぶつけることで、日単位の勝ち負けが確認できます。
一方で生産スケジューラは日単位の山積み結果として判明したライン能力のあふれ分が、前倒し(もっと早く割付ること)すれば納期に間に合うのかどうかを知るために100%の負荷を超えない前提で山崩しを行い、生産計画は負荷計画と不可分なものであるという思想で設計されています。
-

-
生産スケジューラによる無限能力山積みと有限能力山崩しの違い
通常のMRPは無限能力負荷山積みと呼ばれ、オーダが生産能力の範囲内に収まるかどうかを確認しますが、生産スケジューラの有限能力負荷山崩しでは納期遅れしない実現可能なスケジュールを作成できるかどうかを確認します。
続きを見る
インドネシアでMRP(資材所要量計画)システムの運用が難しい理由
資源所要量計画(MRP)は基準生産計画(MPS)を元に所要量展開を行い、在庫を差し引いた正味所要量を計算すると同時に、リードタイム分だけバックワード割付で前倒し(早くする)することで購買オーダや製造オーダの発行タイミングを計算しますが、「製造ロットサイズ」と「リードタイムずらし」の影響で、生成された製造オーダがどの所要(MPS)に紐付いているかが見えにくくなります。
一般的に製造ロットサイズと製造リードタイムは品目ごとにバラバラであり、MRPにより所要量展開された結果としての製造オーダーを受注オーダーと紐付ける作業が複雑になり、生産管理部は計画外で工程ごとに指図を発行するようになりますが、計画外指図は手間がかかり、現場も目標生産数があるのに指図に縛られるのは負担なので、生産管理部と現場の思惑が一致した結果、計画外製造実績(指図なし)という運用になりがちです。
またMRPの基本は正確な正味所要量の計算にあるため、所要量の不足は時間制約違反を無視して、納期遅れ(時間制約違反)したオーダも「前倒し」して紐付けることで、余分なオーダを生成しない仕組みであるため、受入確定量として余分なオーダを出さないようにする機能がシステムを運用する人間から見たとき、オーダ間の紐付けを見づらくします。
内示情報と確定受注オーダーは期間がオーバーラップしますので、システム上では二重登録にならないよう考慮する必要がありますが、内示を確定で置き換える方法としては「新規の確定受注のみを追加して内示は洗替する」ことであり、理屈ではこれにより確定受注の二重登録と内示の二重登録が同時に防止されます。
一般的に計画系機能の発行済製造指図(製造残)は実績系機能の受注残・発注残・発行済みインボイスなどに比べてデータ管理が不明確であるため、内示情報が確定受注に差し替えられるたびに、発行済製造指図への影響がないように、製造指図は確定受注からのみ確定するなどのルールが必要です。
出荷7日分をまとめて製造する場合、受注オーダ品目である製品の出荷7日分を1製造ロットとしてまとめて製造指図を発行する」ということであり、まとめ対象である製造オーダ品目は最終工程の出力品目である製品になります。同じように材料所要量10日分を1購買ロットとして購買指図を発行する場合、まとめ対象である購買オーダの出力品目は材料になります。
-

-
インドネシアでMRP(資材所要量計画)システムの運用が難しい理由
インドネシアでMRP(資材所要量計画)システムの運用を難しくする理由は、品目ごとに異なる「製造ロットサイズ」と「リードタイムずらし」の影響で、生成された製造オーダがどの所要に紐付いているかが見えにくくなる、内示を確定受注で引き落とす際に、指図済み製造オーダーとのリンクを考慮するのが難しいなどです。
続きを見る
インドネシアでできる生産スケジューラによる機会損失と在庫過多のリスク低減
工場が抱える問題には直接的に制御できない納期遅れや過剰在庫(従属変数)が挙げられますが、その大きな原因となり得るものとして、直接的に制御可能であるボトルネック工程の生産性(独立変数)がありますが、ボトルネック工程の生産効率を100%にキープ出来れば、工場の生産能力を100%発揮することができます。
本来在庫には受注リードタイムを製造リードタイムが超える日数分の安全在庫、ボトルネック工程を止めないためのバッファという2つの意味がありますが、現実には受注残(機会損失)リスクを恐れて多めに生産してしまい過剰在庫になるか、在庫コストを恐れて発注のタイミングが遅れて過少在庫となります。
生産スケジューラの導入効果はリードタイム短縮と在庫削減によるキャッシュフロー改善と、受注から製造・購買まで一気通貫の見える化ですが、部品構成・サイクルタイム・品目工程・ロットサイズ・標準梱包数などのマスタ情報と現状在庫数が正確であるという前提条件があります。
基本的には1人の担当者が全工程の生産スケジュールを一気通貫で作成することで最大の効果が出るわけで、生産に流れを作るために生産スケジューラを導入したにも関わらず、従来どおりに計画担当者が複数人でバケツリレー式に計画を立てるというのは本末転倒です。 インドネシアでできる生産スケジューラによる機会損失と在庫過多のリスク低減 インドネシアは市場の需要変動に対応できる生産計画作成のために生産スケジューラを導入する日系製造業社が増えてきましたが、在庫が必要な理由、在庫がコストである理由、機会損失と在庫過多のトレードオフの関係、の観点から生産スケジューラ導入の手順と効果について説明いたします。 続きを見る

インドネシアの日系製造業が求める多面的な収益管理と納期遅れさせない生産管理
インドネシアの製造業で頻繁に見られる問題が、営業部門と出荷部門の分断により受注残管理が出来ない、その結果生産管理部が作成する生産スケジュールを無視した製造部門の独自裁量による生産ですが、この問題の元凶は適正な製品在庫管理が出来ていないことです。
本来であれば営業部門は生産管理部門と一緒に基準生産計画(製品の完成日基準)作成に関与し、出荷部門に出荷指示を出し、受注オーダーに対してどれだけ出荷されたか、どれだけ残っているかの管理、いわゆる受注残管理を行います。
ところが慢性的に出荷時に製品在庫が不足すると、顧客との窓口が営業部門ではなく出荷部門になってしまうことで、受注オーダーと出荷スケジュールの紐付きが切れ、製造部門は出荷を満たすために独自の裁量で生産するようになることで、生産管理部門の生産スケジュールが形骸化します。
-

-
インドネシアの日系製造業が求める正確な原価管理とより多面的な収益管理
インドネシアのコロナ禍の中で、日系製造業様からいただいたシステム化(DX化)のご相談の傾向として、正確な原価管理とより多面的な収益管理の必要性と、納期遅れしない生産管理に対する意識の2点が挙げられます。
続きを見る
インドネシアでグローバル競争を勝ち抜くものづくりを支える生産管理システム
インドネシアにおける製造業が直面する課題として、経済成長に伴い国民の所得水準が上がり、SNSを中心とした情報ツールの発展もあって、最終消費者の嗜好の多様化する一方で、モノと情報の洪水の中で飽きが来るのも早く、製品寿命が短くなりました。
その結果サプライチェーン上での需要予測が難しく受発注数量は小ロット化し、頻繁にオーダ変更が発生し、その負担はサプライチェーンを流れるなかで乗数的に波及効果を及ぼし、適正在庫コントロールを難しくし、機会損失を防ぐあまり保守的になり、どうしても在庫コストが増える傾向があります。
サプライチェーンの中で在庫が少なすぎると出荷の機会を失う受注残リスクが高まる一方で、在庫が多すぎると在庫金利がかかるというトレードオフの問題がありますが、この問題を解消するためには、社内の生産設備の供給能力を考慮した生産計画作成システムの構築が必要になります。
供給能力を考慮することで工程間が無理なく繋がり、製造リードタイムが短縮されることにより工程内在庫が削減され、自動的に在庫金利コストが下がるため、キャッシュで持てる期間が増え、会社の損益に貢献します。
-

-
インドネシアでグローバル競争を勝ち抜くものづくりを支える生産管理システム
インドネシアの製造業が直面する多品種少量化、製品寿命の短命化、小ロット化による製造負荷増大という問題に起因するサプライチェーン上の機会損失と在庫コストというトレードオフの問題を解消するために、供給能力を考慮した需要予測を行うためのシステムの設計方法です。
続きを見る
インドネシアの現場の努力を会社の競争力に変える生産管理業務のシステム化の手順
「大口のお客様に対して限られた品種を安定して納品することだけを考えていればいい」時代から多品種少量化の流れにより、製造への負担が増えました。
限られた設備の中で多品種少量化をこなしていこうとすれば、生産ラインを細分化して、共用ラインを増やすことで全体の稼働率を上げようという話になるのですが、小ロットになると工程ごとのリードタイムが短くなりますので必然的に、金型交換とか洗浄とかの段取り替えが増えます。
初工程投入から完成までの全体の製造リードタイムがばらつくことで、納期回答が難しくなる、現場ではオーダとの紐付きが見えにくいので優先順位をつけきれないので、納期遵守率が悪化する、資材不足によるライン停止を避けたいあまり資材・仕掛品在庫過多になってしまうという問題が発生します。
インドネシア工場の課題の一つとして労務費の高騰がありますが、そのときの出来高を挙げるための手段の一つとして、能率アップ(工数削減)があり、購買から製造、出荷という社内サプライチェーンの流れの中で、時間短縮によって時間と社内リソースの付加価値が上がります。
ただしやみくもに時間短縮すればいいという話ではなく、前工程の能率だけあがっても、後工程がそれにあわせるだけの能率がないと、仕掛品在庫だけが増えていくことになり、一部門だけの最適化が、必ずしも全体で最適化にならない、付加価値は上がらないということです。 インドネシアの現場の努力を会社の競争力に変える生産管理業務のシステム化の手順 インドネシアの製造業は、年々膨らむ国内市場の需給変動に比例して生産方式が多様化するため、オーダ変更に応じて適切に計画の見直しを行い、現場に出された生産指示に対する進捗が見える化されるような工程管理が重要になっています。 続きを見る
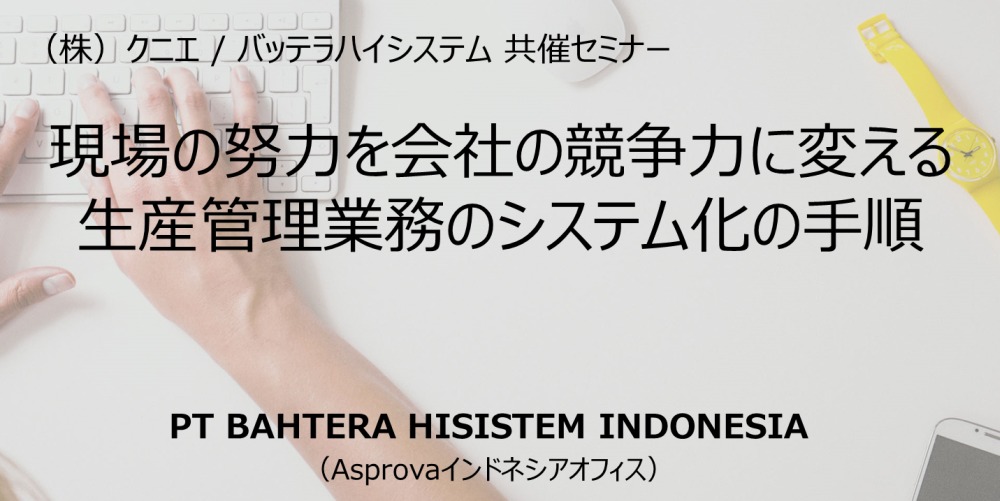
インドネシアで生産スケジューラの営業と導入を行う際のポイント
インドネシアで製造業の生産計画作成業務の自動化は難しいのではないかと言われますが、自動車部品、消費財、化学液体製品などさまざまな業種で生産スケジューラAsprovaが活用され効果を発揮しています。
ただインドネシアではまだ生産スケジューラ自体の知名度が低いため、『生産計画作成業務の自動化』が費用対効果をもたらすだけの価値あるものということを納得していただくのに苦労するのですが、『作業者の負荷計画の自動化』という切り口で説明すると、インドネシア人生産管理担当者には受けることが多いです。
生産管理システムは過去の実績データを元に現状分析を行うシステムであるとすれば、生産スケジューラは数々のパラメータの設定を駆使して、欲しい結果が出力されるようにリスケジュールを繰り返すシステムであり、お客様側が「こんなことできますか?」と聞いてきたら、仮に生産スケジューラでできることだとしても、その場で実演できなければ「できない」のと同じです。
生産計画に影響を及ぼす要素は膨大かつ複雑で、必然的に生産スケジューラも計画パラメタ、マスタ、オーダなど、多くのプロパティを装備しており、それらを「正しく」設定したとしても必ずしも望みどおりの最適化されたスケジュール結果が得られるというわけではなく、あくまでもスケジュール結果に特定の傾向を与える程度でしかありません。
生産計画の最適化を最大公約数的に表現すれば「キャパオーバーしないように、納期遅れもしないように、稼働率を平準化した生産計画」と言えるかもしれませんが、インドネシアのように需要変動、為替変動、物流網の混乱などの影響を受けやすい国ではそのときの市場環境に応じて最適化の定義は変化し、今現在の製造現場にとっての最適に近づけるよう生産スケジューラでシミュレーションを行います。
民間企業においても人治主義的商慣行が色濃く残っており、製造業において納期やコストに対する意識よりも、人の管理にこだわる傾向があると感じます。
1998年にスハルト政権が崩壊し、複数政党による民主的選挙、憲法改正を繰り返しシビリアンコントロールと三権分立を確立させたインドネシアの議会制民主主義の歴史は浅いことが影響しているのかもしれません。
また外国人は人事業務に就くことを禁じられており、建国五原則パンチャシラの下で民族の多様性を重視するためには、インドネシア人を評価できるのはインドネシア人のみという理念が反映されているのだと思います。
-

-
インドネシアで生産スケジューラの営業と導入を行う際のポイント
インドネシアでの生産スケジューラの知名度はまだまだ低いですが、金型や人員など副資源の日別負荷計算や、それらを制約条件とした機械など主資源の生産スケジュール作成という、高額なERPパッケージにも出来ない生産管理業務のコアの部分に対応しています。
続きを見る
インドネシアでの生産管理システム運用上の課題となる製造指図の発行と実績入力
受注情報に基づく生産計画を製造現場にブレイクダウンする上で重要な意味を持つのが製造指図であり、製造指図に対して実績を入れることが生産管理システムの運用上の最大の難関であると同時に、生産管理システムの導入の成否の大きな判断基準となります。
受注情報と生産計画の紐づきを明確に維持したまま製造指図を発行し実績を入れるためには、生産管理システムのMRP機能を運用することになり、Excelでの製造指図発行は現場との乖離を招きやすく受注情報とのリンクが不明確になりやすいです。
-

-
インドネシアでの生産管理システム運用上の課題となる製造指図の発行と実績入力
受注情報に基づく生産計画を製造現場にブレイクダウンする上で重要な意味を持つのが製造指図であり、製造指図に対して実績を入れることが生産管理システムの運用上の最大の難関であると同時に、生産管理システムの導入の成否の大きな判断基準となります。
続きを見る
COMインターフェイスを通したAsprovaの機能の拡張
Asprova本体は、イベントの発生タイミングにプラグインを実行させるためのHookを用意しており、このイベントを表すアクセスポイントであるプラグインキーが、Wordpressのdo_actionフックまたはapply_filtersフックに該当します。
ADOを通してDBアクセスするまでのミドルウェアやコンポーネントの関係は、荷送人(Shipper)から荷受人(Consignee)に荷物を海上輸送する過程に似ています。
開発アプリケーションプログラム(Shipper)からRDBやExcel, Texfile(Consignee)にアクセスするには、OLE DBデータプロバイダーという仲介人(Forwarder)に手続きをお願いしますが、直接OLE DBとやりとりするのはややこしい書類手続きなど煩わしいので、ADO(カーゴ業者)にやってもらいます。
-

-
COMインターフェイスを通したAsprovaの機能の拡張
生産スケジューラAsprovaはCOMインターフェイスを公開し、EXEファイルやプラグイン(DLL)で機能を拡張することができます。EXEファイルやDLLファイルからメモリー上に展開されているプロジェクトオブジェクトを取得し、Asprovaの下位のテーブルオブジェクトにアクセスします。
続きを見る
生産スケジューラの実績が作業とオーダのステータスに与える影響
生産スケジューラAsprovaでは、すべての作業は日時固定レベルと数量固定レベルを持っており、作業をマニュアルで移動させると日時固定レベルが10になるのでリスケジュールにより前後作業が引き寄せられ、また作業に実績数量を入れると日時固定レベルが40になるのでリスケジュールにより後工程作業の計画数量が実績数量で上書きされます。
-

-
生産スケジューラの実績が作業とオーダのステータスに与える影響
生産スケジューラAsprovaでは、生成された作業を完了させると該当作業を含むオーダが着手済みになり、作業を計画済みに戻すとオーダは未着手に戻り、オーダを完了させると該当作業すべてが完了しますが、オーダを未着手に戻しても作業実績は消えず計画済みに戻りません。
続きを見る
金型や作業者などの制約を設備の生産スケジュールに反映する方法
設備投資は簡単に今日明日中にできることではないですが、作業者は配置転換や新規採用など、低コストで柔軟に対応できる部分なので、作業者のキャパ計画で主資源の稼働率を上げることは工場経営において非常に大きな意味があります。
金型交換時間を主資源の前段取り時間に設定すれば内段取り(ラインや機械を止めて行う段取り)になり、主資源CUTの前段取りタスクに120分、副資源の前段取りタスクに0を設定すると、内段取り時間120分の間は機械をストップすることになります。
金型交換時間を副資源の前段取り時間に設定すれば、外段取り(ラインや機械を止めずに行う段取り)になり、主資源の前段取りタスクはブランク、副資源の前段取りタスクに120分を設定すると、外段取り時間120分の間も機械は稼動し続けます。 金型や作業者などの制約を設備の生産スケジュールに反映する方法 金型の保有数や金型交換にかかる段取り時間、金型と資源とのマッピング、メンテナンススケジュールなどは、主資源を基準とした生産計画に大きく影響し、作業者や金型などの主資源に対する制約条件となる副資源を生産計画に反映させることができます。 続きを見る

生産スケジューラで作成する組み立て系とプロセス系の生産計画の違い
プロセス系製造工程では一貫ラインを使用するため、自工程作業と次工程作業が連続して行われ、空き時間が発生することはなく、ましてや他オーダの作業が間に割って入ることはありません。
またプロセス系製造工程ではタンクを使うケースが多く、自工程でのタンク内での調製作業が完了し、次工程に流れ終わるのを待つ間、自工程で作業は発生しないが中身が流れてしまうまでの間、タンクに他のオーダを割り付けたくない、という制約が発生します。 生産スケジューラで作成する組み立て系とプロセス系の生産計画の違い パッケージシステムが組立系製造工程向きに開発されているのは業務の標準化がし易いからであり、プロセス系は一貫ラインを使用するため、自工程作業と次工程作業が連続して行われ、空き時間が発生することはなく、他オーダの作業が間に割って入ることはありません。 続きを見る

生産スケジューラで作成する原材料在庫の制約条件を加味した生産計画
原料在庫のあるオーダから先に生産するような計画を作成するために、生産スケジューラAsprovaでは、バックワード割付時に「受注オーダから生成される原料の補充オーダのうち、棚卸在庫以外の購買オーダや発注残から紐付いているもの」を先に割り付けていくことで、自然と最後に棚卸在庫に紐付くオーダが割りついていくことで、材料在庫のあるオーダから先に生産する計画が作成されます。
-

-
生産スケジューラで作成する原材料在庫の制約条件を加味した生産計画
原料を使用する初工程からフォワードで割り付ければ自然と在庫を先に消費する計画が出来ますが、出荷に近い後工程からバックワードで割り付ければ仕掛品の製造オーダを先に生成し最後の不足分に在庫が割り当てられるため、在庫の消費優先という計画にならない可能性があります。
続きを見る
生産スケジューラAsprovaで出来る標準原価計算
Asprovaの品目テーブルには、品目の内訳である原価費目別に原料単価、賃率、配賦率を設定するのですが、Asprovaには固定費予算から賃率や配賦率を自動計算する機能はないため、Asprovaの外で、Excelを用いて計算した結果を品目テーブルに設定します。
-

-
インドネシアでもできる生産スケジューラによる標準原価計算
生産スケジューラーAsprovaに原価費目別に単価や賃率、配賦率が設定できれば、予定生産数量や予定工数を計算することができますので、販売予測に基づいて来期の予算を製品別、製品グループ別、機械別、顧客別に計算することができます。
続きを見る
インドネシアでAIを活用した最新の生産スケジュール作成方法
生産スケジューラAsprovaのSolverというオプションのコマンドに、機械学習(Machine Learning)の遺伝的アルゴリズム(Genetic Algorithm)による生産スケジューリング最適解の探索ロジックが実装されたことで、これまで難しいとされた相反するトレードオフの関係にある条件を満たす最適値を高速で見つけることが出来るようになりました。
インドネシアでこれまで難易度が高かった生産スケジューラの導入が、ITを専門としないコンサルティング会社や営業会社でも出来るまでに難易度が下がったことは、最新のAIによるパラダイムシフトが、生産スケジューラをコモディティ化することを意味します。 インドネシアでAIを活用した最新の生産スケジュール作成方法 製造業の生産ラインのスケジューリングでは、遺伝的アルゴリズムという機械学習により生産効率の最適解を探索することが出来るようになり、インドネシアでもAIのコモディティ化が製造業システムの分野においてパラダイムシフトを起こしています。 続きを見る