会計は1つの取引を借方と貸方に2面的に分けて記帳し費用と収益の差額を純資産に組み入れ「資産=負債+純資産」が均衡するパズルのような仕組みです。発生主義の取引入力を前提とした上で現預金の動きを把握するために現金主義への修正を行うのがキャッシュフロー管理です。 インドネシアの会計システム インドネシアでキャッシュレス化が浸透し、銀行口座を通して行われた企業取引がすべてシステムに自動仕訳されることで日常的な記帳業務はなくなれば、人間がマニュアルで会計業務に絡む場面は少なくなることが予想されますが、頭の中に業務の基本を体系的に記憶することは重要だと考えます。 続きを見る
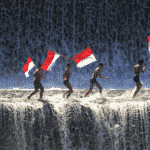
当ブログでシェアしたい会計情報とは
インドネシアで20年近く業務システムを導入してきた経験の中で、現場での担当者との会話から得たITや業務に関連する知識、プロジェクトを進める上で苦労した点などを当ブログにまとめています。
これがインドネシアに来て自分の本職以外の業務にも対応せざるを得なくなり、頭を抱えている駐在員や出張者の方々にとって、何等かの不安解消の材料になれば、これほどうれしいことはありません。
当ブログへの日本からのアクセス数は、インドネシア関連のエントリーよりも会計関連のエントリーのほうが圧倒的に多く、特に他勘定振替や賃率計算、有償支給無償支給の仕訳などについてのエントリーは、企業の経理担当者や情報システム部の方々に見ていただいているようです。
-

-
インドネシアにおける外注先への有償支給と無償支給
有償支給であれ無償支給であれ、外注先にP/O発行し、材料倉庫の材料を引当、材料の出庫指図を発行し出庫実績を計上し、外注先での支給品使用実績を計上し、外注入荷実績を計上するという処理の流れは同じですが、外注先に発行するP/O価格には有償支給の場合は材料費+加工費、無償支給の場合は加工費のみ含まれています。
続きを見る
業務システムの仕事をする上で会計の知識が必ずしも必要というわけではありませんが、インドネシア人の経理担当者と会話するには、知識があったほうがより深い議論ができるのは間違いありません。
僕は学生時代に会計士を目指そうと考えたことがあり、手始めに日商簿記二級に合格後、一級を目指して勉強しましたがあえなく不合格。
当時は学生生活のすべてを試験勉強に捧げるほどの根性もなく、さらにインド古典音楽に興味を持ってからは、長期休み期間中はほとんどインドに行ってしまい、会計士への夢は潰えました。
当時所属していた中国武術会の後輩S君が2年生に進級すると同時に会計士試験に集中するために退部してしまい、僕の卒業後に見事に現役4年生で合格したという連絡をもらったとき、S君の頑張りを見てきた僕としては、祝福と嫉妬が入り混じった複雑な気持ちの中、あそこまで完全に試験勉強にコミットするのは絶対無理、というあきらめの感情もありました。
自分には会計士ほどの専門知識はありませんが、会計学や簿記などの座学では得られない、会計システム導入と運用の現場で得た知識と経験をシェアできたらと考えております。
会計には金額がスライドパズルのように一致する面白さがある
会計には1つの取引を借方と貸方に2面的に分けて記帳した1か月分の仕訳のリストから、費用と収益に関する項目のみ抽出して引き算した結果得られる利益(損失)を、純資産に組み入れることで「資産=負債+資本(純資産)」がバランスする「スライドパズル」のような仕組みがあります。
利益が出れば出るほど資本が膨らんでいきますが、損失が出れば出るほど資本が縮小していき、現預金がショートした時点で会社としてのゲームオーバーとなります。
借方と貸方に該当する取引すべて
- 資産の増加 <-> 資産の減少
- 負債の減少 <-> 負債の増加
- 資本の減少 <-> 資本の増加
- 費用の増加 <-> 費用の減少
- 収益の減少 <-> 収益の増加
当月(当期)の損益をP/L(損益計算書)で算出し、その結果として資産、負債、純資産の状態がどうなったかを知るためのものがとB/S(貸借対照表)であり、すべての数字の根拠は上記の現実世界の取引から発生します。
現実世界で発生する取引に時間の概念を持ち込んで物理的に発生していない取引を起こす難しさ
現実世界は上下、左右、前後から形成される3次元の世界ですが、会計ではこの3次元空間で発生した取引に、時間の概念を導入して4次元空間を意識して記帳していきます。
例えば機械や検査機器などの固定資産を購入する場合、現金払いまたは掛け(ツケ)にすることによって自分の所有物になります。
そしてその固定資産を使用することが、直接的にも間接的にも利益に貢献する場合には、貢献した分だけ費用計上して売上から差し引かないと公正な利益にはならないという考えをします。
このように現実世界で取引が発生していないにもかかわらず、過去に購入し取得した機械(固定資産)や文房具(貯蔵品)、前払した保険料(無料または割引で治療を受ける権利という資産)などを、当月の売上を獲得するために貢献したものと考え、資産の貢献分を金額に換算して費用計上します。
3次元での現実の取引に時間の概念が増えて4次元になる。ドラえもんのポケットが4次元空間に繋がっているように、過去のある時点に発生した支払いが、未来に遡って現在(当期)費用化する取引の代表的なものが減価償却費、経過勘定(前払費用)、貯蔵品です。
減価償却費
過去に購入した固定資産は当月の売上に貢献したとみなされるため、貢献分を費用化する。固定資産は取得価額はそのままに、減価償却累計額で間接的に帳簿価額を計算する。
- Dr. 固定資産 900 Cr. 預金 900
- Dr. 減価償却費 10 Cr. 減価償却累計額 10
前払保険料
過去に支払った1年分の保険料のおかげで、当月は病院で無料または保険割引で治療を受けられる。
- Dr. 前払保険料 80 Cr. 預金 80
- Dr. 保険料 10 Cr. 前払保険料 10
貯蔵品
過去に支払った貯蔵品のうち、当月消耗した分は当月の売上に貢献したと見なされる。
- Dr. 貯蔵品 90 Cr. 現金 90
- Dr. 消耗品費 10 Cr. 貯蔵品 10
このように現金の収入や支出に関係なく、経済的事象の発生または変化にもとづいて、その時点で収益または費用を計上することを発生主義の原則といい、業務システムへの入力は会計も含めて基本は発生主義ベースで行われます。
4次元の話から時間軸を消して3次元の現金の動きに戻す難しさ
せっかく発生主義の原則にもとづいて、頑張って現実世界の取引に時間軸の概念を取り入れて、4次元に話をまとめたのに、また3次元に戻すってどういうこと?とも思いますが、理屈では発生主義とか言っても、現実世界ではキャッシュの有無が会社の生死を決めますので、当月の現金の動きと残高を把握するには、発生主義ベースで作成したP/Lを現金主義ベースに修正する必要があります。
この発生主義ベースの実績入力を前提とした上で、手元で自由に動かせる真水の資産、すなわち現預金の動きがどれくらいあるかを把握するために現金主義への修正を行うのがキャッシュフロー管理です。
会社が儲かるというのはあくまでのP/L上で利益が出ているということであり、
- 債権債務が発生済み未決済の費用と収益
- 減価償却費分
を調整してキャッシュフロー計算書を作成することで、現金主義で直近の決済に対応するための経営情報が得られます。
3次元のモノの背景によって価値が異なる難しさ
現実世界では同じ製品でも前月からの在庫と当月製造されたものとでは評価額が異なり、出荷されたものには両方が混じっているため、売上原価の内訳は厳密には以下のようになります。
- 前月からの製品在庫単価x出荷数量
- 当月製造分の製品単価x出荷数量
つまり現実世界で同じように見える製品でも、いつ生産されたかという背景によって評価額が異なり、「製造原価=売上原価」となるのは売れるものだけ作る完全受注生産の場合のみ成立し、在庫を多くかかえる事業体ほど製造原価と売上原価の乖離が大きくなる傾向があります。
- 今月購入した材料の費用が当月購入材料費
- 月初の材料在庫と今月購入した材料のうち、今月投入した材料の原価が当月材料費(発生)
- 今月の直接労務費と製造間接費が当月加工費
- 月初の仕掛在庫と当月材料費と当月加工費のうち、今月完成した製品の原価が製造原価
- 月初の製品在庫と今月完成した製品のうち、今月出荷した製品の原価が売上原価
現実的にはインドネシアの会社法と社内リソースの兼ね合い、経営管理部のサジ加減で可能な限り正確な評価額を計算してB/Sの棚卸資産の部に反映させるのですが、実際の棚卸作業で数え間違えがあれば出てきた数字は間違ったものとなります。
材料と仕掛品の棚卸が過少だと生産のためにたくさん投入したと見なされ製造原価が増え利益が減り、逆に棚卸在庫を過多で評価してしまうと生産のために少なく投入したと見なされ製造原価が減り利益が増えてしまいます。
「学生時代に何を勉強すべきか」というテーマ
僕の学生時代は国際社会に対応するための英語と、経済的センスを磨くための簿記会計を勉強しとけと言われていました。
近年人気上昇しているのは世界中どこでも仕事ができるWEBプログラミング、そして最近では人生遠回りするよりも経済的自由を身につけるために、学生時代にお金を稼ぐ方法(起業)を身につけるべき、という意見もあります。
英語が社会に出てから必要になるというのは当時でも周知の事実であり、インドネシアで仕事をしている現在でも、英語が上手いインドネシア人の中で英語が下手な日本人だと相当恥ずかしい思いをします。
プログラミングは、当時の任意選択科目コンピューターサイエンスの実習で、8インチのディスケット(その後フロッピーディスクと呼ばれるもの)を使ったFORTRUN77というプログラミング言語で、面白くもおかしくもないロジックを組まされて嫌気が差した思い出しか残っていませんが、今みたいにPCとインターネットが普及していれば、独学でいつでもどこでもタダでWEBサイト構築の勉強が出来ます。
英語とかプログラミングは、自分がそれを武器に格好良く仕事をする情景が目に浮かぶので、勉強するモチベーションも上がるというものですが、簿記会計については財務諸表が読めるようになるとか言われても、なんか薄暗い経理部の部屋でおっちゃんが夜遅くまで電卓たたいて金勘定しているドラマのシーンが脳裏に浮かび、それでどんだけ自分にとってメリットがあるのかイメージ湧かないと思います。
文系の人間は専攻がはっきりしないので、理系の人間に対して一種のコンプレックスがあり、特に僕の場合商学部のマクロ経済寄り、金融経済のゼミという特徴の掴みにくい専攻だったため、大学で学んだことの痕跡を残すという意味でも、バカのまま卒業する前にせめて簿記試験くらい受けておこうという程度の意識低い系でした。
背景に会社継続の制約とお金の流れがイメージできない話は胡散臭い
会社で経理部に配属されたり会計士を目指す人は別として、一般の人でも簿記会計を少し勉強していると、テレビやネットで目にするニュースを見聞きする際に、「この会社(人)何を売って儲けているんだろうか?」とか「どの勘定科目で処理するんだろう」くらいのことは意識するようになります。
フリーランスでも製造業でもサービス業でもすべての事業は最終的にお金で評価されますので、そこにいたるまでのすべての取引は会計仕訳に置き換えられ、P/L(損益計算書)とB/S(貸借対照表)に反映されるまでにはプロセスがあり、例えば下のようなネットでよく目にする何気ない言葉にも取引が発生しています。
- 毎月ン百万稼いでます
Dr.預金 Cr.売上 - ン億円の資金調達に成功(第三者割当増資のケース)
Dr.預金 Cr.資本金 - 東南アジア戦略の一角としてインドネシアへ進出(現法設立)。
Dr.預金 Cr.資本金 - ビットコインで億りました(売却したケース)。
Dr.預金 Cr.仮想通貨
Cr.売却益 - 世界中を旅しながらフリーランスとして生きています。
Dr.預金 Cr.売上 - 不労所得で好きなことだけやって生きてます(ブログでアフィリエイト)。
Dr.売掛金 Cr.売上 (確定時)
Dr.預金 Cr.売掛金 (振込時)
このように事業を立ち上げて売上が立ち、預金口座にキャッシュが増える一方で、事業を継続するためには常に費用がかかりますので、例えば資本金10,000の会社が毎月2,500の費用を計上できるのは4ヶ月間のみであり、資本金の源泉である預金(お金)がなくなる前、売上を立てないと資金がショートし会社は倒産します。
会社を設立した月に自分のお金が会社の資産(預金)に変わる。
- Dr. 預金(お金)10,000 Cr. 資本金 10,000
最初の数ヶ月はオフィスの備品を揃えたり商品の仕入を行ったり費用だけがかかる。
- Dr. 費用 2,500 Cr.預金(お金)2,500
翌月にようやく売上が立つ。
- Dr. 預金(お金)8,000 Cr. 売上 8,000
つまり事業による売上は、資金がショートする前に当座預金にキャッシュを補充しなければならないという制約の下で繰り返されるのであり、上記のようなキラキラした事象の背景に、この基本的な会社継続の制約とお金の流れが具体的にイメージできないと、どこか胡散臭さが感じられます。
この感覚はおそらく銀行の融資担当者が融資を受けに来た人の話を聞いて、事業が継続可能なもので元本と金利を返済可能なものであるかどうかを審査する際に感じるものに近いのではないかと想像します。
不正なお金の流れにも必ず会計取引が発生している
外部監査によって有価証券報告書(投資家の投資判断の資料等にするため、事業年度ごとに会社の業績をまとめて国と証券取引所に提出する書類)の内容が適切であることを保証される上場企業が、億単位の金額を簿外で取引することは極めて難しいので、不正な取引が発覚する際にはもっともらしい別の勘定科目に付け替えられているのが普通です。
- 販売費及び一般管理費(販管費)への「付け替え」
⇒日産のCEO予備費から販売促進費として中東日産に流れたお金がオマーンの代理店をトンネルにしてゴーンさん保有の投資会社に流れる。 - 有償支給による「循環取引」
⇒東芝が液晶ディスプレイ製造を外注先へ有償支給する際に、売上を二重計上することによる水増し。 - セールスコミッション・コンサルタント料として「移転価格」
⇒日本債権信用銀行やオリンパスなど、タックスヘブンであるケイマン諸島の現地法人に移転価格し税金対策。
先日4月4日に日産の前会長カルロス・ゴーン容疑者が、中東オマーンに不正送金して会社に損害を与えたという会社法違反(特別背任)容疑で4度目の逮捕されました。
昨年2018年11月19日と12月10日の逮捕は役員報酬を総額50億円も過少申告したことにより日産の有価証券報告書が虚偽記載と判断されたことにより、金融商品取引法違反が適用されました。
金融商品取引法違反ではゴーンさん自身の不正を立証できるかどうかが争点でしたが、当然ながら日産のP/L上の販売管理費科目である役員報酬が過少に記載され、差額は別の販売管理費科目に付け替えられている可能性があります。
- Dr. 役員報酬 50億円 Cr. 当座預金 50億円
その後12月21日に個人の資産管理会社と新生銀行との間のスワップ契約の損失を日産に付け替えた容疑による特別背任で3回目の逮捕がされましたが、日産に損失の実害が発生したことを立証できず2019年3月6日に保釈されてしまいました。
ところが今回の会社法違反(特別背任)はもう完全に漆黒のクロ、日産から中東日産、オマーンの販売代理店SBAを経由してゴーンさん保有の投資会社に送金させた38億円以外にも、ゴーンさん個人の大型クルーザー購入費用や4人の子供のスタンフォード大学費用が、日産の会計上で架空の販管費として計上され、私的流用された疑いがあるそうです。
- Dr. 販売促進費 38億円 Cr.CEO予備費 38億円
「不適切会計」と記載される経済ニュースは、だいたい税逃れ・私的流用・粉飾の3種類のどれかが目的になっており、いずれも有価証券報告書の虚偽記載は免れないため、P/LとB/Sの数字もおかしくなったことにより一番被害を被るのは株主になります。
日産は自動車メーカーであり、自動車を生産するまでの材料費や労務費などのコストはすべて製造原価の中に納まっており、今回の事件はすべてCEO予備費(CEOリザーブ)というゴーンさんの裁量で支出できる準備金から販売管理費として計上されています。
つまりゴーンさんの4度目の逮捕によって日産のイメージダウンは免れないとはいえ、本業のモノ作りを行う製造現場には何の責任もないということは強調する必要があると思います。
(2020年1月追記)
カルロスゴーン被告は12月30日に日本を不法出国しレバノンに逃走しました。
タックスヘイブンと移転価格
僕が新卒で入社したのは旧長期信用銀行系のシステム会社でして、最初に配属されたのがAS/400上でRPG(Report Program Generator)とCL(Control Language)ベースで海外支店用システムを開発・運用する部門でした。
当時の海外支店一覧の中でロンドンとかニューヨークとか有名都市に混じって、ひときわ異色を放っていたのがケイマン支店であり、最初はナニコレという感じでした。
当時の先輩からは、ケイマン諸島というのは税金が優遇された特別区なので、日系の銀行はほとんど全部がケイマン諸島に支店を置いて節税している、と教えてもらいました。
その後僕自身はインドネシアに転職してしまい、その名前もすっかり忘れていたところに、2013年のオリンパスの損失隠し事件で、ケイマン諸島の会社買収がなんかおかしい、みたいな感じで突然懐かしい名前として自分の前に登場しました。
不動産や金融資産で大損こいたら、その含み損は時価会計の原則で損失処理を行なうべきですが、僕がちょうどインドネシアに来た1997年に発生した山一證券の破綻の場合は、含み損のある不動産を簿価で連結対象外の関連会社に売却し、関連会社の損失に計上させるという典型的な「飛ばし」になります。
ただオリンパス事件は2013年最近の話であり、こんなベタな飛ばしは通用する時代じゃなくなっていましたので、実質無価値なペーパーカンパニーを過大な評価金額でM&Aして、損失穴埋めの裏金を捻出すると同時に、財テクの損失をM&Aの損失に「付け替え」という方法だったようです。
ケイマン諸島には、島内で事業を行わない会社は法人税を払わなくて良いという法律があり、がめつい海外企業からの出どころ不明の租税回避マネーを呼び込んで、会社設立、運営、送金手数料などなどで財政をまかなおうという、人口の少ない国だからなせる技を取っています。
こういうのをまさにランチェスター戦略と言うんでしょうけど、実際島の住民約5万人はほぼ無税で社会保障も充実している中で幸せに暮らしているそうです。
実際のところ、僕の前職の親会社である銀行のように、世界中の大企業がペーパーカンパニーを設立して、ケイマン支店をいろんな形で節税対策として利用しているようです。
株主の利益最大化という企業の目的には合致しているとはいえ、一般庶民の感覚からすれば自国に納税せずに庶民の税金でまかなわれる公共サービスにタダ乗りしているんじゃないの、と外野席からヤジの一つでも飛ばしてやりたいところです。
関係ないですが、僕がインドネシアに転職する数ヶ月前に、この銀行の系列会社である不動産リース会社でバブル崩壊による巨額不動産損失が発覚し、銀行から子会社出向してきていた当時のダンディな部長さんが、実はこの事件に深く関与していたということで、ニュースステーションに緊急出演するなど、随分会社内外でゴタゴタしていた時期でした。
結局はこの事件が引き金になって銀行自体が消滅することになりました・・・。
話がズレそうですが、日本で移転価格税制が導入されたのが1986年とのことで、僕が日本で働いていたのが1995年前後ですから、日本で発行した長期金融債の運用益を、海外支店とはいえども別事業会社であるケイマン支店に、コンサルタント料とか販売手数料とかいう名目で費用計上し安易に送金したら、間違いなく移転価格と見なされていたはずです。
勘定科目としてのロイヤルティと配当
会計システム導入時には、なにはともあれ勘定科目を準備していただく必要があるのですが、日本本社がインドネシア拠点から投資回収するための科目として、ロイヤルティ(Royalty)と配当(dividend)があります。
ロイヤルティは、製造費用科目の場合はProduction Royalty、販管費科目の場合はコミッション(Sales Commission)、配当は未払配当金(Dividend Payable)として負債科目にクラス分けされることが多いです。
このロイヤルティはインドネシア現地法人と日本本社間の関所みたいな科目であり、そこにはインドネシアの税務署という門番が二重三重にガードを固めており、最悪の場合は通行拒否(価格移転と判断され否認)されます。
うまく関所を抜けられた(日本本社に対する正当なロイヤルティとして認められた)としても、移転価格税制に基づきロイヤルティ金額を再計算された上で、PPh26という通行税(海外サービスに対する源泉税)20%を支払う必要があります。
ただ日本とインドネシアは租税協定がありますので、「海外支店間取引につき日本側で一定額納税しますからインドネシア側でも軽減税率を適用してください」と申告することができます。
そしてインドネシア側で源泉徴収票(Bukti potong PPh26)を発行してもらい、日本の税務署に提出することで「インドネシアで一定額は源泉済み」という証明をすることで二重課税は避けられます。
本来配当という形での投資回収が望ましいのでしょうが、インドネシアの税務署は企業が数年間連続して営業利益を出していない限り、配当へ計上を否認するというのが現状です。
移転価格と利益操作
先日、日本で開発されたパッケージソフトウェアをマレーシアの海外拠点から購入する際に「値引き販売は日本で価格移転と見なされかねないのでインドネシアだからと言って優遇は出来ません」と言われてしまいました。
価格移転とか利益操作という意図ではなく、好意で行なった値引き販売が、当局によって疑われてしまうというのは、なんとも切ないところです。
インドネシアでも「お友達価格」というのは非常に危険であり、「お得意さんだから今回は利益なしで提供します」というのは税務署から利益操作取引と見なされかねず、結局お互いの利益にならないため、やらないように気をつけています。


